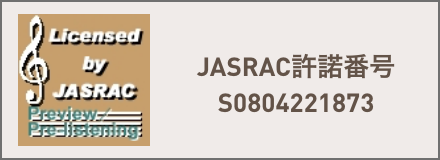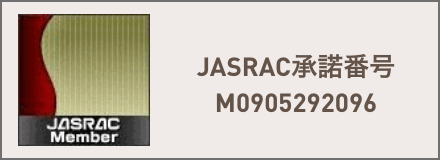スペイン舞曲集より(4. ビリャネスカ 5. アンダルーサ 6. ホタ):エンリケ・グラナドス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]
・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料
・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可
・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷
・International Shipping
- 作曲: エンリケ・グラナドス
編曲: 米山邦宏 - 編成:S.sax. (* A.sax.)/A.sax./T.sax./B.sax.
- 演奏時間:0:15:25
フォスターミュージック/FME-0273
- 概要
- 編成/曲目
- 補足
- ENGLISH
スペイン舞曲集より(4. ビリャネスカ 5. アンダルーサ 6. ホタ)
エンリケ・グラナドス(1876-1916)は、スペイン東北部カタルーニャ地方生まれ。作品はピアノ曲が多いが、オペラ「ゴイェスカス」、歌曲集「トナディーリャス」などの名作も書いている。戦時に不遇の死を遂げなければ、まだまだ名曲が生まれたことだろう。グラナドス・アカデミーを設立し、後進の指導にも力を入れていた。この学校からはアリシア・デ・ラローチャなど現代を代表するスペインのピアニストが生まれている。
全12曲からなるこの作品は、グラナドスの作品の中でも最も有名だろう。アルベニスがアンダルシアなど南部の作風が多いのに対して、グラナドスは北部の舞曲から作られた曲が多い。中間部に歌を持つA-B-Aの形式が多い点でも、アルベニスラローチャによると、作者が自ら書いた副題は第4番、7番のみで、他は後に出版社が書いたものと言う。
●第4曲「Villanesca」 原調:G dur 演奏時間:0:05:19
ビリャネスカとは田園風とか牧歌風といった意味で、素朴な感じを意識して演奏しよう。高音部に現れるCのオクターブ連続が、規則的に動く水車小屋のようなイメージにも聞こえる。マーチの様に拍表を強く、拍裏を弱く、少し大げさに吹くと田舎くさく聞こえてくるが、節度を持って朴訥とした中にも上品さを保ちたい。
●第5曲「Andaluza」 原調:e moll 演奏時間:0:04:01
この曲はまさしくアンダルシア的な曲で、おそらくこの曲集の中でもっとも演奏される機会が多い曲だろう。もともとギターの模倣曲といわれるだけあり、ギターへのアレンジが非常に多く名演も多い。
アンダルシア地方独特の情念を感じる旋律と揺らぐリズムは、南部スペイン独特の雰囲気をかもしだすので、そういった名演を参考にするのも役に立つだろう。
●第6曲「Jota」 原調:D dur 演奏時間:0:06:05
ロンダリア舞曲ともいわれるホタは、おもにアラゴン地方で奏され、専門の楽団があるぐらい著名な舞曲だ。軽妙な3拍子でゆったり始まり、クレッシェンドしながら加速していくという民族舞曲に多い形式を踏襲している。中盤で盛り上がりきらないようにコントロールしよう。中間の Molto andante の部分はテンポの揺らぎが難しい。copla と呼ばれる短詩型の歌は朗々とespressivo に歌われ、合いの手の伴奏で a tempo となる。歌の部分の a piacere とは、自由に、気ままに、という意味なので、全員の呼吸をそろえる練習が大切だろう。
仕様
- アーティスト
- 作曲: エンリケ・グラナドス
編曲: 米山邦宏
- 演奏形態
- サクソフォン
- 編成
- 4重奏
- 演奏時間
- 0:15:25
- 商品形態
- アンサンブル楽譜(Full Score & Part)
- 出版社 / 品番
- フォスターミュージック / FME-0273
- JANコード
- 4560318471122
- 発売日(年)
- 2014/12/17
- キーワード
- クラシックアレンジ, ,
NAXOS Music Libraryで聴く
楽器編成
- Full Score
- Soprano Saxophone (optional Alto Saxophone)
- Alto Saxophone
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
米山邦宏(Kunihiro Yoneyama)
1959年生まれ、音楽は父親である米山正夫(昭和の作曲家)より手ほどきを受ける。
小学校よりクラシックギターを始め、フラメンコ、タンゴなどの演奏へ幅を広げ、南米の音楽を得意としている。
吹奏楽分野ではユーフォニウム、ギター、ベース、コントラバス等を演奏。
現在はオリジナル作品の作曲・アレンジ作品の受注製作、各種レコード音源の作成、ギター教育、歌唱教育などを行う。
どんなジャンルでも書けるクリエイターを目指しており、演歌・歌謡曲からクラシック、ラテンまで幅広く対応している。
- サイズ
- A4/1cm未満
12 DANZANSESPANOLAS OP.37 - IV. VILLANESCA V. ANDALUZA VI. JOTA
Specifications
- ARTIST
- Composer: Enrique GRANADOSArranger: Kunihiro YONEYAMA
- INSTRUMENTATION
- Saxophone / Quartet (4parts)
- DURATION
- 0:15:25
- PRODUCT TYPE
- Set / ENSEMBLE (Full Score & Part)
- PUBLISHER / Code
- fostermusic Inc. / FME-0273
- JAN
- 4560318471122
- RELEASE
- 2014/12/17
- OVERSEAS SHIPMENT
- Yes
- EUROPEAN PARTS
- Not Included

![スペイン舞曲集より(4. ビリャネスカ 5. アンダルーサ 6. ホタ):エンリケ・グラナドス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]](/html/upload/save_image/FME0273_1.png)