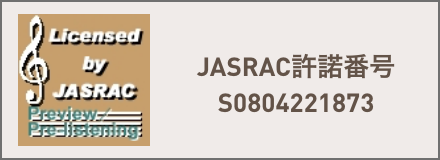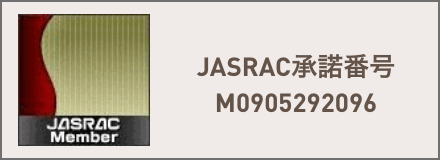スペインの歌(3. 椰子の木陰で 4. コルドバ 5. セギディーリャ):イサーク・アルベニス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]
・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料
・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可
・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷
・International Shipping
- 作曲: イサーク・アルベニス
編曲: 米山邦宏 - 編成:S.sax. (or A.sax.)/A.sax./T.sax./B.sax.
- 演奏時間:0:15:17
フォスターミュージック/FME-0279
- 概要
- 編成/曲目
- 補足
- ENGLISH
スペインの歌(3. 椰子の木陰で 4. コルドバ 5. セギディーリャ)
イサーク・アルベニス(1860-1909)は、スペイン東北部カタルーニャ地方に生まれ、後期にはイギリス、フランスへと移り住み、フォーレ、ショーソン、ドビュッシーなど著名なフランス音楽の作曲家たちと交流を持ち、影響を受けたと伝えられている。
作品は、管弦楽曲、ピアノ協奏曲、サルスエラ(スペイン風オペレッタ)なども数曲あるが、ほとんどがピアノ独奏曲である。
5曲からなるこの作品は、スペイン組曲と同じぐらい有名な曲であり演奏頻度も多い。アルベニスがパリに定住していた以降の作品と考えられており、作風も精緻でさらに洗練された作品が多い。
オペラ「ペピータ・ヒメネス」を作曲したのもこの頃であり、作曲家として充実していた時期だったのであろう。スペイン組曲と同様に民族主義を強く感じる組曲となっている。
●第3曲「Bajo la palmera」 原調:Es dur 演奏時間:0:04:38
Orientalとはうってかわって明るい曲調で、カリブ海に浮かぶ諸島やキューバなど、南国のイメージがよく描写されている。ハバネラやダンサ・クバーナ(キューバ舞曲)のリズムがベースにはなっているが、「スペイン組曲」の第8曲「Cuba」と同じように複雑なポリリズムが構築されており、「3連符+8分音符2つ」のリズムや旋律が多く登場する。前後でしっかり切り分けて演奏するより、一つのフレーズとして「加速しつつ入り、ゆっくりと抜ける」ように奏すると、この曲に内在するゆったりとたゆたうような感じが出るだろう。
●第4曲「Cordoba」 原調:d moll 演奏時間:0:06:47
冒頭の響きは、メスキータ(モスク)の鐘の響きを模倣しているので、是非そのように奏してほしい。
この雨紛は約50小節続くので、静かに荘厳な感じを維持していたい。その後スペイン的なリズムに乗って新しい主題が現れるが、次曲「Seguidillas」のようなリズムを重視した演奏より、上品に流れるような旋律にした方がこの曲の美しさが表せる気がする。この主題は長調に転調し、さらに高揚を見せるが、ここでも節度を持った高揚感を維持していたい。中間でいきなり第一主題のメスキータ部分が現れるが、節度のある高揚を保つことによって美しく繋がるだろう。その後またアンダルシアの旋律になるが、高揚感はなく、余韻に酔いながら静かに終焉に向かう。大変美しい曲である。
●第5曲「Seguidillas」 原調:Fis Dur 演奏時間:0:03:52
アルベニスが常套手段としているA -B - Aの形式を取らず、中間部に歌がないこの曲は、終始セギディーリャスのリズムに乗って奏される。リズムと交互に現れる copla とも呼べるような歌の部分(con anima の部分)は、tempo rubato で奏されることも多く、リズムに戻ったところで a tempo で戻すのも面白いだろう。Fis dur という調で書かれてはいるが、内部的にはきわめて転調が多い。目まぐるしく変わる調性はすべて臨時記号で記載されているため、どの調にいるかを常に意識し、記号を落とさないように注意して演奏してほしい。
仕様
- アーティスト
- 作曲: イサーク・アルベニス
編曲: 米山邦宏
- 演奏形態
- サクソフォン
- 編成
- 4重奏
- 演奏時間
- 0:15:17
- 商品形態
- アンサンブル楽譜(Full Score & Part)
- 出版社 / 品番
- フォスターミュージック / FME-0279
- JANコード
- 4560318472792
- 発売日(年)
- 2014/12/17
- キーワード
- クラシックアレンジ, ,
NAXOS Music Libraryで聴く
楽器編成
- Full Score
- Soprano Saxophone (or Alto Saxophone)
- Alto Saxophone
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
米山邦宏(Kunihiro Yoneyama)
1959年生まれ、音楽は父親である米山正夫(昭和の作曲家)より手ほどきを受ける。
小学校よりクラシックギターを始め、フラメンコ、タンゴなどの演奏へ幅を広げ、南米の音楽を得意としている。
吹奏楽分野ではユーフォニウム、ギター、ベース、コントラバス等を演奏。
現在はオリジナル作品の作曲・アレンジ作品の受注製作、各種レコード音源の作成、ギター教育、歌唱教育などを行う。
どんなジャンルでも書けるクリエイターを目指しており、演歌・歌謡曲からクラシック、ラテンまで幅広く対応している。
- サイズ
- A4/1cm未満
CANTOD DE ESPANA OP.232 - III. BAJO LA PALMERA VI. CORDOBA V. SEGUIDELLAS
Specifications
- ARTIST
- Composer: Isaac ALBENIZArranger: Kunihiro YONEYAMA
- INSTRUMENTATION
- Saxophone / Quartet (4parts)
- DURATION
- 0:15:17
- PRODUCT TYPE
- Set / ENSEMBLE (Full Score & Part)
- PUBLISHER / Code
- fostermusic Inc. / FME-0279
- JAN
- 4560318472792
- RELEASE
- 2014/12/17
- OVERSEAS SHIPMENT
- Yes
- EUROPEAN PARTS
- Not Included

![スペインの歌(3. 椰子の木陰で 4. コルドバ 5. セギディーリャ):イサーク・アルベニス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]](/html/upload/save_image/FME0279_1.png)