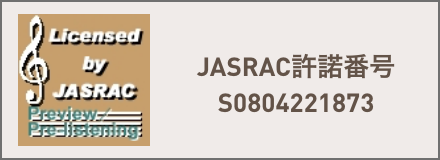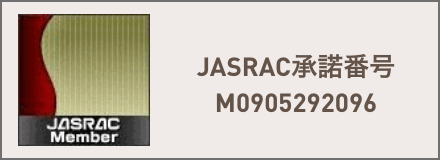12月25日15時を持ちまして、
2025年内出荷の注文受付を終了いたしました。
以降のご注文は年明け
【 2026年1月7日(水)以降順次出荷 】
となります。予めご了承ください。
本年もたくさんのご愛顧を賜りありがとうございました。
よいお年をお迎えください。
スペイン組曲 第1集 Op.47(4. カディス 6. アラゴン 8. キューバ):イサーク・アルベニス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]
・1配送につき税込11,000円以上のご注文で国内送料無料
・コンビニ後払い、クレジットカード、銀行振込利用可
・[在庫あり]は営業日正午までのご注文で即日出荷
・International Shipping
- 作曲: イサーク・アルベニス
編曲: 米山邦宏 - 編成:S.sax./A.sax./T.sax./B.sax.
- 演奏時間:0:14:04
フォスターミュージック/FME-0277
- 概要
- 編成/曲目
- 補足
- ENGLISH
スペイン組曲 第1集 Op.47(4. カディス 6. アラゴン 8. キューバ)
イサーク・アルベニス(1860-1909)は、スペイン東北部カタルーニャ地方に生まれ、後期にはイギリス、フランスへと移り住み、フォーレ、ショーソン、ドビュッシーなど著名なフランス音楽の作曲家たちと交流を持ち、影響を受けたと伝えられている。
作品は、管弦楽曲、ピアノ協奏曲、サルスエラ(スペイン風オペレッタ)なども数曲あるが、ほとんどがピアノ独奏曲である。
8曲からなるこの作品は、アルベニスの作品の中でも最も有名で演奏頻度も高い作品であるが、
作曲者による編纂ではなく、出版社が後に構成し、出版時に組曲化された作品である。個々の作品はどれもスペインの民族色を強く打ち出した作風であり、聞いているだけでスペインの風景が浮かぶような秀逸な組曲となっている。
●第4曲「Cadiz」 原調:Des dur 演奏時間:0:03:58
もともとはセレナータ・エスパニョーラと名付けられた曲であり、ファンダンゴ系の独特のリズムに支えられたとてもスペイン的な曲である。スペインのカディス地方とは直接の関係はない。序盤からTの2拍目に登場する三連符は、ファンダンゴのリズムの一環であり、装飾的な吹き方にならないように注意したい。原調でアレンジしているため、中間部でEのフリギアなど、調号が多くて吹きにくい部分も出てくるが、早いパッセージではないので、一つ一つ正確に練習して欲しい。
●第6曲「Aragon」 原調:F dur 演奏時間:0:04:59
ホタ・アラゴネーサと呼ばれるこの曲は、東北アラゴン地方のリズムであるホタをベースに書かれている。ホタは明るく軽妙なリズムに終始する曲が多い民謡のような曲であり、バンドゥーリアやラウード、ギターなど、民族色豊かな器楽合奏で奏でられ、中間部で copla と呼ばれる短詩形の民謡が歌われることが多い。小さく始まり徐々に高揚していく曲だが、中間部直前の最大の盛り上がりに照準を合わせ、それ以前に登りつめてしまわないように演奏したい。その copla の部分では、歌の部分と伴奏の部分でリズムが緩急大きく変わるので、各パートの呼吸がそろうように注意してほしい。
●第8曲「Cuba」 原調:Es dur 演奏時間:0:05:13
6/8拍子で書かれているが、序奏リズムは3/4拍子とのポリリズムになっている。また5小節目から始まる第一主題は後半に2連符をともない、リズムを取りにくく感じるかもしれない。キューバはスペインに統治されていた時期が長く、このような複合リズムが多く存在する。サルサ、レゲエ、メレンゲなどの独特のリズムも、こういったポリリズムをベースに培われた物かもしれない。日本人にはなかなか扱いにくいリズムだと思うが、この機会に自分のものにしてしまおう。音符自体はそれほど難しくないので、リズムに慣れれば大きなレパートリーになるだろう。中間部に歌を持つアルベニスが得意なA-B-Aの形式で、中間部は存分に歌い上げたほうが美しいだろう。
仕様
- アーティスト
- 作曲: イサーク・アルベニス
編曲: 米山邦宏
- 演奏形態
- サクソフォン
- 編成
- 4重奏
- 演奏時間
- 0:14:04
- 商品形態
- アンサンブル楽譜(Full Score & Part)
- 出版社 / 品番
- フォスターミュージック / FME-0277
- JANコード
- 4560318472778
- 発売日(年)
- 2014/12/17
- キーワード
- クラシックアレンジ, ,
NAXOS Music Libraryで聴く
楽器編成
- Full Score
- Soprano Saxophone
- Alto Saxophone
- Tenor Saxophone
- Baritone Saxophone
米山邦宏(Kunihiro Yoneyama)
1959年生まれ、音楽は父親である米山正夫(昭和の作曲家)より手ほどきを受ける。
小学校よりクラシックギターを始め、フラメンコ、タンゴなどの演奏へ幅を広げ、南米の音楽を得意としている。
吹奏楽分野ではユーフォニウム、ギター、ベース、コントラバス等を演奏。
現在はオリジナル作品の作曲・アレンジ作品の受注製作、各種レコード音源の作成、ギター教育、歌唱教育などを行う。
どんなジャンルでも書けるクリエイターを目指しており、演歌・歌謡曲からクラシック、ラテンまで幅広く対応している。
- サイズ
- A4/1cm未満
SUITE ESPANOLA NO.1 OP.47 - IV. CADIZ VI. ARAGON VIII. CUBA
Specifications
- ARTIST
- Composer: Isaac ALBENIZArranger: Kunihiro YONEYAMA
- INSTRUMENTATION
- Saxophone / Quartet (4parts)
- DURATION
- 0:14:04
- PRODUCT TYPE
- Set / ENSEMBLE (Full Score & Part)
- PUBLISHER / Code
- fostermusic Inc. / FME-0277
- JAN
- 4560318472778
- RELEASE
- 2014/12/17
- OVERSEAS SHIPMENT
- Yes
- EUROPEAN PARTS
- Not Included

![スペイン組曲 第1集 Op.47(4. カディス 6. アラゴン 8. キューバ):イサーク・アルベニス arr. 米山邦宏 [サクソフォン4重奏]](/html/upload/save_image/FME0277_1.png)